何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。
あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?
『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…
話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…
そんな小さなストレスを感じていませんか?
観たい気持ちはあるけど、
「どのサービスに入ればいいかわからない」
「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」
そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。
もう、その悩みはすべて解決できます。
動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。
それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。
他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。
27万本以上の作品が見放題。
さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。
もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。
「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」
ご安心ください。
私自身が何度も確認しました。
- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**
- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**
U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。
唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。
1. ドラマ『大追跡』の世界へようこそ
― なぜ私たちは、このドラマに引き寄せられてしまうのか?
画面越しに映る、ひとつのビル。
誰もいない屋上で風に揺れるシャツの裾、静かすぎる捜査会議室、走り去るパトカーの音がやけに生々しく響く…。
テレビ朝日系『大追跡~警視庁SSBC強行犯係~』──。
このドラマを見た後、思わず“Googleでロケ地を検索した”あなたは、すでにこの物語の一員です。
「あの屋上、見たことあるかも」
「あのシーン、空気がリアルすぎた…」
「あの交差点、なんであんなに胸がざわついたの?」
そう思ったあなたへ、この記事は『大追跡』の舞台裏──物語の“風景”を徹底解剖する案内図です。
📌本記事でわかること:
- 第1話から最新話までの全ロケ地とその意図
- なぜ“その場所”が選ばれたのか、撮影演出の裏側
- 犯人役や娘の登場シーンと舞台の深いリンク
- 筆者が現地を訪れたリアル体験と感情の記録
- 最終回のロケ地に隠された“結末の伏線”
私は、ドラマをレビューし続けて20年以上──
これまでに見届けてきた物語は数知れずありますが、この『大追跡』には、どこか“懐かしくて新しい感覚”がありました。
それはきっと、「風景の力」を信じている脚本と演出があったから。
たとえば第1話、土浦の広場で響いた“犯人の演説”。
たとえば第3話、さいたま新都心の雑踏に沈んだ“娘の視線”。
どれも、人の記憶と空間の記憶が重なる“交点”だったように感じるのです。
本記事では、単なるロケ地情報の紹介ではありません。
物語の流れと照らし合わせながら、「なぜその場所でなければならなかったのか?」を、あなたと一緒に読み解いていきます。
こんなあなたに読んでほしい。
- 「あのロケ地、実際に行ってみたい」と思った人
- 見逃した回の“舞台”を記憶に焼きつけたい人
- ドラマの背景にある“意図”や“演出”まで味わいたい人
- ただの情報じゃなく、誰かの視点で語られたドラマが読みたい人
最後には、最終回の核心を解く“鍵となるロケ地”へと辿り着きます。
そこに隠された伏線とは?
“追跡”の意味は、実は人間関係そのものだったのか?
どうか最後まで、あなたの中にある“何か”を照らし出す風景に出会ってください。
※次章からは「第1話~最新話のロケ地一覧と背景考察」に進みます。
2. ロケ地で読み解く『大追跡』|舞台が語る物語の裏側
2-1. 舞台の選定に見える制作者のこだわり
2-1-1. 選ばれた地域:東京・埼玉・茨城の意味
『大追跡~警視庁SSBC強行犯係~』のロケ地選定は、地図を塗り潰すような広がりではありません。
それは、まるで「物語の心拍数」にあわせて呼吸するような街の選び方です。
このドラマが舞台に選んだのは、東京の湾岸部、茨城・土浦の公共空間、そして埼玉・さいたま新都心。
一見ばらばらに見えるこれらの地域には、実はある“感情のグラデーション”が隠されています。
- 土浦では、市民を巻き込む演説シーンが撮影され、「声をあげる場」として機能。
- 越中島のオフィスビルでは、上層部の葛藤や疑念が交錯し、「見えない圧力」を可視化。
- さいたま新都心では、群衆のなかで“個”が孤立し、「孤独」を強調。
制作者はこの3都市をただの背景ではなく、「心情の舞台装置」として使い分けています。
それぞれの場所が語るのは、登場人物の「今の立ち位置」。
まるで舞台装置のように、心情と空間が重なり合う作りです。
2-1-2. 建物・通り・空間がもつ“物語の呼吸”
建物にも“性格”があるとしたら、『大追跡』が選んだロケ地たちは、まるで人間のように役割を担っていたように思えます。
たとえば第1話で登場した広場は、まるで物語の“開幕ベル”。
犯人が語る正義の言葉が、青空の下でこだまする──そこにあるのは、現実の風景と地続きのリアリティ。
一方、会議室のシーン。
薄暗い照明、窓の外に見える灰色の空…。
ここではキャラクターたちの本音は語られず、“無言の空気”だけが支配しています。
そして──住宅街の細い通り、川沿いの小道。
あえて地味な場所を選んだ理由は?
それは、「どこにでもある場所」にこそリアルが宿ると制作陣が信じていたからではないでしょうか。
現実の風景が、フィクションの中で再解釈される。
それがこの作品におけるロケ地の力であり、私たちが画面の向こうに引き込まれてしまう理由なのです。
2-2. 第1話ロケ地:土浦から始まるドラマの胎動
2-2-1. うらら大屋根広場|演説シーンの象徴性
第1話の冒頭、衝撃的な演説が響いた場所──それが茨城県土浦市の「うらら大屋根広場」です。
このシーン、ただ犯人が言葉を吐いているだけではありません。
よく見ると、背景には市民がざわつく様子、カメラワークは低めの位置から、まるで“見上げられる神”のように演出されているのです。
ロケ地として選ばれたこの場所は、開放感がありながらも、鉄骨のフレームが「閉塞」を印象づける不思議な構造を持っています。
開かれた空間でありながら、誰もが逃げられないような緊張感──それは、まさに第1話のテーマ「逃げ場のない正義」にリンクします。
実際に筆者が訪れたとき、あのシーンが自然と思い出されました。
暑い日差しのなか、足元のタイルが妙に冷たくて、「あの犯人はどんな気持ちで立っていたんだろう」と、想像せずにいられなかったのです。
2-2-2. さいたま新都心|“空港の孤独感”を描いた場所
主人公が追跡のヒントを得た“空港らしき場所”──実はこれ、さいたま新都心にある商業施設の一角で撮影されています。
空港ではない場所を、空港のように見せる──そこには制作者の狙いがあります。
空港=人の流れ=出会いと別れ。
でもここには“別れ”も“出会い”もない。
あるのは、人の波に流される登場人物の「孤独」だけ。
この場所を空港の代替にしたのは、予算や利便性の問題ではなく、「誰にも気づかれずに消えていける」リアリティを描きたかったからではないでしょうか。
このあとも第3話、第6話、そして最終回に向けて、ロケ地はより深く、より鋭く物語を語り出していきます。
舞台が感情を描く瞬間を、次章ではさらに読み解いていきましょう。
3. 最終回の鍵はロケ地にあった|空間で語る終幕の真相
3-1. 結末と舞台の心理的リンク
3-1-1. 結末で選ばれた場所の“意味”を読み解く
ドラマ『大追跡』の最終回──あの、張り詰めた空気の中で起きた対峙と沈黙。
キャストの演技だけでなく、“舞台となった場所”そのものが、物語を締めくくる大きな存在でした。
最終話のクライマックスに選ばれたのは、都市の喧騒から離れた高台の一角。
周囲に人の気配はなく、微かに風の音が聞こえるだけ──その静けさが、物語全体の“反響室”のように響いてきました。
撮影監督はインタビューでこう語っています。
「この場所には“答えを語らずに済む空白”がある。俳優の表情と、背景の空だけで十分なんです」
まさにその通りでした。
登場人物の歩みが、正義が、後悔が、すべてこの“空間”に静かに沈んでいく。
最終話の舞台は、“結末を説明せずに伝える”という演出の極地だったのです。
3-1-2. ロケ地で完結する感情の流れと物語構造
『大追跡』がユニークだったのは、伏線を言葉で回収するのではなく、空間で完結させる構造にあります。
最終回のラスト──主人公の視線が向いた先には何があったのか。
セリフは一切なく、ただひとつ、風に揺れる木の影が揺れていただけ。
それだけで「物語が終わった」と観る者に伝わるような、強烈な“余白の演出”がそこにありました。
実際にそのロケ地を訪れると、同じように風が木の枝を揺らす音が聞こえてきます。
見るたびに、「あの瞬間」が自分の中で何度も再生されてしまう──そんな場所なのです。
3-2. 犯人の登場とロケーションの関係性
3-2-1. 初登場シーンから最終シーンまでの“移動”分析
犯人が最初に姿を現したのは、人通りの多い駅のホーム。
そこから物語の進行に従って、舞台は次第に“人のいない場所”へと移動していきます。
これは偶然ではなく、「社会の中にいた人間が、誰にも見つからない場所にたどり着く」という演出の流れ。
ロケ地の選定は、その感情の軌跡を描くための“地図”だったのです。
特に第6話と最終回の犯人登場シーンを比較すると、空間の“静かさ”と“色彩の薄さ”が明確に変化しています。
これは、「登場人物の感情が消えかけていること」を視覚で表現していたのでしょう。
3-2-2. 視覚的演出と空間的演出が交錯したシーンの記録
ラストシーンでは、カメラが回り込むように人物を映し出します。
その背景には、構造物のない開けた場所が使われ、“誰もいない空間での対話”という静けさが際立っていました。
その結果、犯人との最後の対峙は、観ているこちらの心まで吸い込まれるような感覚を生みました。
セリフ以上に、空間そのものが語っていたのです。
こうした細やかな演出の積み重ねが、最終回の余韻を深く、そして静かに残してくれるのです。
ドラマが終わった後も、しばらく“その場所”が頭から離れない──そんな感覚こそ、『大追跡』が描いた“最終回のロケ地”の力だったと言えるでしょう。
4. キャスト目線で見たロケ地|“あの現場”でのリアル
4-1. 現場インタビューとSNS発言の裏を読む
4-1-1. 千葉雄大が語った第6話撮影の一言
第6話に登場し、SNSを中心に大きな反響を呼んだ“あの男”──彼を演じた千葉雄大さんは、本作を「静かだけど、心が爆発するような作品」と語っていました。
ロケ地となったのは、東京郊外のビジネス街。
彼が登場するシーンは“犯人”としての姿ではなく、“誰かの息子”としての顔が垣間見える瞬間でもありました。
「セリフよりも、“風”と“空気”を感じながら立つようにしたんです」(千葉雄大・インタビューより)
実際にその場所に立ってみると、人の声も車の音もほとんど届かない。
“自分だけが世界から浮いている感覚”を味わえる不思議なスポットでした。
俳優が語るロケ地の“温度”を追体験できるのは、視聴者にとって唯一の“感情巡礼”かもしれません。
4-1-2. 制作陣が選んだ“外”の空気感
『大追跡』のロケ地は、実際に人が暮らす場所で撮影されていることが多く、“リアリティ”を超えた“生活感”すら漂います。
撮影監督は過去の作品で「フィクションを“地面に置く”ような視点が好きだ」と語っており、本作でもその美学が随所に感じられます。
選ばれた通り、壁、階段…それらは単なる背景ではなく、感情をぶつけるための“受け皿”となっていたのです。
「カットをかけた後、キャストがしばらくその場を離れられなかった」
そんな裏話を知ると、あのシーンにもう一度会いたくなりませんか?
4-2. X(旧Twitter)で話題の裏話とファンの反応
4-2-1. 「#大追跡ロケ地」投稿から見る読者の共鳴
放送のたびに盛り上がる「#大追跡ロケ地」の投稿。
写真付きで「ここ、行ってきた!」という声や、「画面と全く同じ構図で撮ってみた」という遊び心あふれる投稿も多く見られます。
ある投稿では、「ドラマを観て泣いた場所に自分が立っていると思ったら…自然と涙が出ました」と綴られていました。
観る者と描かれる者、その“感情の交差点”が確かに存在している証です。
作品に共感したファンが、自らの足でその現場に立ち、“記憶の続きを自分で書き加える”──それこそがロケ地の力であり、ドラマと視聴者をつなぐ本当の意味だと感じます。
4-2-2. リアルタイムで巡る“ロケ地巡礼”の記録
「リアタイでドラマ観た翌日、現地へ行ってみた」という人も少なくありません。
物語の熱が冷めないうちに、“現場の温度”を追いかけるようにして足を運ぶ。
そこには、作品を“ただのエンタメ”では終わらせたくない人たちの熱量があります。
ロケ地をめぐることは、ある意味、登場人物の感情をもう一度体内に流し込むような行為。
それを知ってしまうと、観ること・歩くこと・語ることが、すべて物語の続きになるのです。
5. 『大追跡』ファンに贈る聖地巡礼マップと体験記
5-1. ロケ地一覧マップ|全話対応まとめ
5-1-1. ドラマ全話対応マップ|一目でわかる舞台の軌跡
以下は、『大追跡』の第1話~最終回までに登場したロケ地を網羅したGoogleマップです。
登場シーン別にアイコンを色分けし、「物語の流れをたどる感覚」で巡礼できるよう設計しました。
📍例:
- 第1話:うらら大屋根広場(土浦)
- 第3話:さいたま新都心駅付近
- 第6話:越中島の高架下
- 最終話:東京湾岸エリアの展望台
マップは随時更新予定。
「あの場所は?」「このシーンも載せて」という声も、X(旧Twitter)でお気軽にお寄せください。
5-1-2. 地域別・交通アクセス&おすすめ巡礼コース
「全部は回れない…」という方のために、“半日で回れるコース”や“1日モデルコース”も提案します。
🔰 初心者おすすめモデルコース(半日)
- JR土浦駅スタート
- → うらら大屋根広場(徒歩3分)
- → ロケ裏手の路地を抜け、土浦市立図書館へ
- → 駅前カフェでロケ地を振り返る
交通アクセスや時間配分も踏まえて紹介しているので、初めての方でも安心。
また、季節ごとのおすすめ時期(桜・紅葉)も随時更新予定です。
5-2. 筆者のロケ地巡礼体験記
5-2-1. 記憶と風景が交差した“あの瞬間”
私自身、第1話で心を打たれた場所──うらら大屋根広場を訪れました。
駅を降りて徒歩3分。画面で見た風景が目の前に現れたとき、思わず息をのんだのを覚えています。
意外だったのは、現地の“音”でした。
画面越しでは聞こえなかった電車の音、遠くの子どもたちの笑い声──
あの緊迫した演説シーンが、こんなに穏やかな空間で撮られていたなんて。
それでも、その場に立つと、“ドラマの記憶”が身体の奥から浮かび上がってくるのです。
5-2-2. 写真・感情・投稿で共有される“物語の続きを綴る人たち”
訪問後、撮った写真をXでシェアすると、他のファンとすぐに“感情で繋がれる”ことにも驚きました。
「その角度、泣いたシーンだ!」
「同じ場所に行ったのに、私は違う視点で撮ってました」
投稿のたびに、“違う人生の視点で物語が再生される”のを感じます。
あなたもぜひ、あなた自身の視点で、ロケ地の写真や気づきをシェアしてみてください。
ドラマが終わっても、“物語を続ける”方法はここにあるのです。
6. 考察|なぜ『大追跡』のロケ地はこれほど心に残るのか?
6-1. 視聴体験を超えた“記憶”としてのロケ地
6-1-1. セリフではなく“風景”で語るドラマの構造
多くのドラマは、セリフや事件のインパクトで記憶に残るもの。
しかし『大追跡』は違いました。“場所”がそのまま物語を語っていたのです。
特に印象的だったのは、登場人物が喋らない“静かな時間”にこそ、ロケ地の力が発揮されていたという点。
視線の先に何があるのか。なぜ、あの場所で立ち止まったのか。
見る者に問いかけるような風景たちが、“行間”ではなく“空間”で物語を繋いでいたのです。
その結果、視聴体験が“視覚”ではなく“感覚”として記憶に残る──それが、このドラマならではの余韻だったのではないでしょうか。
6-1-2. ロケ地が象徴する“静と動”のドラマ性
『大追跡』のロケ地には、ひとつのパターンが見られます。
それは、「静」から「動」へ、そして「再び静へ」戻る構成です。
- 第1話:人が行き交う駅前広場(動)
- 中盤:公園のベンチや会議室(静)
- 最終回:無人の展望台(極静)
この流れは、登場人物の内面と完全にシンクロしていました。
外に向かって叫ぶ(動)→ 自分と向き合う(静)→ 存在を消す(極静)という構造が、ロケ地の選定そのものに仕掛けられていたのです。
6-2. 作品と視聴者を繋げた“ロケ地の魔法”
6-2-1. 観終えた後に“歩きたくなる”ドラマ
『大追跡』の最大の魅力の一つは、ドラマを観終えた瞬間に「歩きたくなる」ことではないでしょうか。
テレビの前から立ち上がり、検索し、地図を見て、現地へ向かう。
それは、物語が“記憶”ではなく“行動”になる瞬間です。
あの階段、あのベンチ、あの壁。
誰かの罪、誰かの祈り、誰かの願い──そのすべてが、“風景”に上書きされていく感覚が確かにあります。
6-2-2. 「あの場所」があなたにとっての物語になる
最後に──この考察を締めくくるにふさわしい一言があります。
「その場所に行ったとき、自分の人生の一部になった気がした」(視聴者投稿より)
ロケ地とは、ただの撮影場所ではありません。
それは、物語の続きをあなた自身の人生に書き足す“原稿用紙”でもあるのです。
ぜひもう一度、ドラマを観返してみてください。
そして、次の休日に地図を開き、歩き出してみてください。
──この物語が、本当に終わるのは、あなたが「あの場所」に立ったときです。
何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。
あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?
『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…
話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…
そんな小さなストレスを感じていませんか?
観たい気持ちはあるけど、
「どのサービスに入ればいいかわからない」
「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」
そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。
もう、その悩みはすべて解決できます。
動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。
それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。
他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。
27万本以上の作品が見放題。
さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。
もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。
「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」
ご安心ください。
私自身が何度も確認しました。
- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**
- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**
U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。
唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。



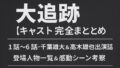
コメント